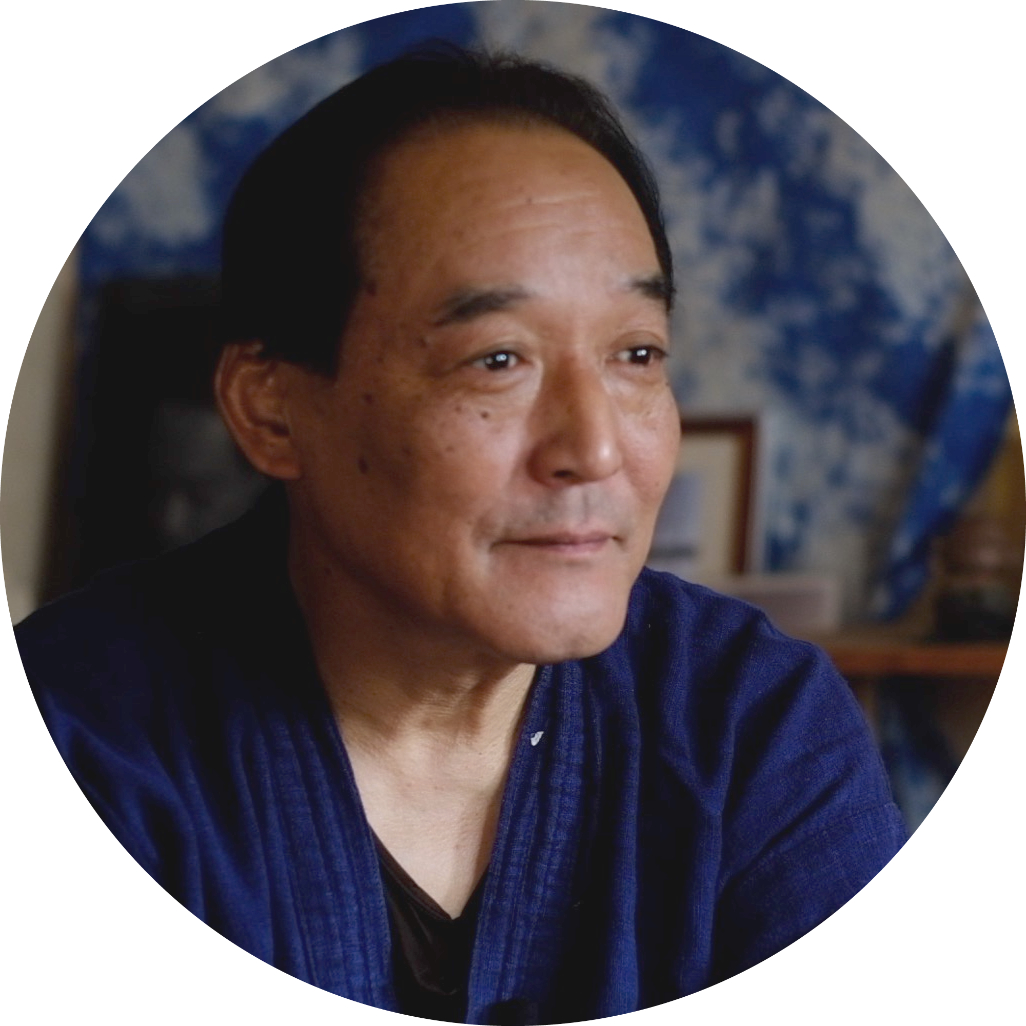島根県を流れる斐伊川のほとり。
この地で7代にわたり、斐伊川和紙の伝統を受け継ぐ職人、井谷伸次(いだにしんじ)さん。
彼の仕事は、伝統を継承するだけに留まらず、素材や人と響き合う、深く、そして人間味あふれる職人の姿が浮かび上がってきます。
職人としての考え方などについてお話を伺いました。
この地で7代にわたり、斐伊川和紙の伝統を受け継ぐ職人、井谷伸次(いだにしんじ)さん。
彼の仕事は、伝統を継承するだけに留まらず、素材や人と響き合う、深く、そして人間味あふれる職人の姿が浮かび上がってきます。
職人としての考え方などについてお話を伺いました。
斐伊川和紙について
斐伊川和紙の成り立ち
- 斐伊川和紙の成り立ちについて教えてください
-
斐伊川和紙の歴史は、約250年前に遡ります。
茶人としても名高い松江藩主・松平不昧公の時代には、この地域は400軒ぐらいあったようです。ほとんどが紙漉き、障子紙などが作られていました。
特にお茶のお殿様が有名だから、茶の湯で使う「懐紙(かいし)」が多く作られており、懐紙の日本三大産地だったようです。
最近では飾るものが増えてきており、アート的な和紙をお客様からご依頼をいただくことも増えています。
職人としての考え方
- 井谷さんの仕事の原点
-
私の仕事の原点は、子供の頃に毎日聞いていた工房の「音」なんでしょうね。
言葉で「こうしろ」と教わったというより、あのリズムが自然と身体に染み込んでいる、という感覚です。
そのことを象徴する、忘れられない出来事が修行時代にありました。
ある日、作業を終えて家族で食卓を囲んでいたら、祖父が私にこう言ったんです。
「お前、今日いい紙を漉いたなぁ」と。
驚いたのは、祖父はその日、工房にはいなかったし、もちろん私の仕事も出来上がった紙も見ていない、ということです。
ただ、私が紙を漉く音を聞いただけで、その日の仕事が「良かった」と分かったんですね。
「いい音・リズム」が紙漉きの極意なんだな、と。
- 仕事で最も集中している時、どんな感覚ですか?
-
無の境地を紙漉きだけで経験したことがあります。
なんて言うんでしょうか…音楽を聴いて仕事をしているけど、水を見てすくう、原料を見ながらやっているという瞬間があるんです。意識していない時がある。もう連続でやって...人間じゃないようで、ロボットみたいな。自分でも、そんな感覚です。
よく、坐禅で「無の境地」なんて言いますけど、あれに近いのかもしれません。
ただ面白いのはね、どうやってその状態に入るか、ということなんです。『俺は今日うまいぞ』なんて、自信満々で絶好調の時。そういう時は、絶対に失敗します。必ず、油断しているんですね。
むしろ、悩んだ時の方が…いい感じでできます。
最初は用心して、「うまくいかないな、どうしよう」と考えながらやっている。そして、少しずつ「あ、うまくいったかな」と感じ始めた、まさにその瞬間から、すっとゾーンに入っていくみたいなんです。
だから、不安や困難の中から生まれる、あの極限の集中。その意識すら消えた先に、自分でも驚くような一番いい仕事が待っている。ものづくりって、本当にそういうものなんだと思います。
- 先代の跡を継ぐ中で、どのようにして『ご自身のやり方』を見つけられましたか?
-
私の成長には、父との静かな対話も欠かせませんでしたね。
修行時代、私が漉いた紙の最終選別は父の役目だったんです。でも、基準に満たない紙があっても、頭ごなしに怒るような人ではありませんでした。
ただ、「まぁなぁ…」と独り言のようにつぶやきながら、その紙をそっと横に置くだけ。父は、何が悪いのかを決して説明しませんでした。あれは父なりの、「自分で考えなさい」という、静かで優しい対話だったんだと思います。
そんな風に温かく見守ってはくれていましたが、やはり偉大な父を持つプレッシャーは常にありましたね。
『お父さんの漉いた紙はよかったのに、もうちょっと頑張ってね』とか言われたことあります。傷つきますよ。相当。
その葛藤から抜け出せたのは、ある時、ふっと「父を越えよう」と思うのを諦めた瞬間でした。
諦めた瞬間に、越えたとは思ってないけど、そういうことを一切思わなくなったんです。そうしたら不思議なもので、今度は私自身の紙を評価してくれるお客様が、少しずつ現れ始めたんです。
- 先代から受け継いだものは、道具だけでなく、他に何がありますか?
-
今、工房で使っている道具は父から受け継いだものです。
いや、『父が使っているのをまだ使っている段階』と言った方が正確かもしれませんね。『実を言うと、おじいちゃんも使っている可能性がある』。
ですから、もう100年近く前のものになるんでしょうか。もちろん、傷んだところは自分で手直ししながら、ずっと使い続けています。
こういう古い道具を使い、昔ながらのやり方をしているからこそ、仕事は毎回が勝負で、『感じること』が大切になります。
例えば、原料の粘りを出すトロロアオイの量。あれは、父から子へ『レシピ』として伝えられるようなものじゃないんです。
なぜなら、私と父では道具の動かし方が違いますから、最適な『程よさ』も当然変わってくる。その絶妙な塩梅を、私は『適当』と呼んでいます。
もちろん、いい加減にやるという意味ではありません。『その時に最も“適”した状態に“当”てる』。熟練の技と言えば聞こえはいいですが、まあ、そういう感覚の世界ですね。
- 井谷さんにとって紙漉きってなんでしょう?
-
結局うちのことを気に入ってくださるお客様がいるということ、人に支えてもらっているということですね。
と言いますのも、私にとって紙漉きは、単にものを作っているという感覚ではなく、紙漉きも、人との交流も、すべてがコミュニケーションのツールなんです。
素材と向き合うのも対話ですし、何より、それを使ってくださるお客様との対話。それが、私のものづくりの中心に、いつもあります。
繊維をどのように見極めて漉く、あのお客様にはこんなふうな漉き方をする。
微妙なことです。思いを込めるとか、そんなことを絶えず繰り返しているとできていくことってあるのではないかと考えています。
斐伊川和紙について
緑豊かな中にある斐伊川和紙の工房。工房に近づくとリズミカルな水と竹の音がとても心地よく感じました。
今回の取材で最も心に残ったのは、お祖父様が実際の紙を見ずに、音だけで「お前、今日いい紙を漉いたなぁ」と、その日の仕事の出来栄えを認められたというお話です。
言葉を超えた感覚の世界、そして職人同士の魂の共感がそこにはありました。一枚の紙が生まれる背景には、これほど豊かな「音」の物語があったのかと、深く胸を打たれました。
井谷さんは「哲学なんて」と謙遜されますが、そのお話は、ものづくりの枠を超え、まるで禅問答のようでした。「悩んだ末に訪れる」というゾーンの話、そして紙を漉くことは素材やお客様との「対話」であるという考え方。一つのことを突き詰めた先にある、澄み切った精神世界に触れたような気がします。
取材を終えて、私たちの身の回りにある「もの」たちが、少し違って見えてきました。その一つひとつに、作り手の声や、目には見えない物語が息づいているのかもしれません。
今回の取材で最も心に残ったのは、お祖父様が実際の紙を見ずに、音だけで「お前、今日いい紙を漉いたなぁ」と、その日の仕事の出来栄えを認められたというお話です。
言葉を超えた感覚の世界、そして職人同士の魂の共感がそこにはありました。一枚の紙が生まれる背景には、これほど豊かな「音」の物語があったのかと、深く胸を打たれました。
井谷さんは「哲学なんて」と謙遜されますが、そのお話は、ものづくりの枠を超え、まるで禅問答のようでした。「悩んだ末に訪れる」というゾーンの話、そして紙を漉くことは素材やお客様との「対話」であるという考え方。一つのことを突き詰めた先にある、澄み切った精神世界に触れたような気がします。
取材を終えて、私たちの身の回りにある「もの」たちが、少し違って見えてきました。その一つひとつに、作り手の声や、目には見えない物語が息づいているのかもしれません。
プロフィール
- 斐伊川和紙
- 690-2511
- 島根県雲南市三刀屋町上熊谷302
- 【TEL】0854-45-3886
- 【HP】https://hiikawawashi.com/